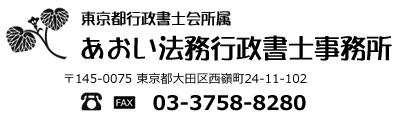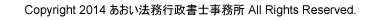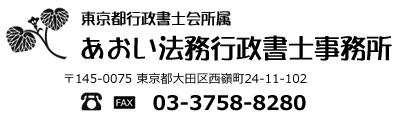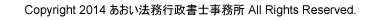| ○ 遺言書の起案及び作成指導 |
残された者たちが、相続財産をめぐって骨肉の争いをしないように未然に防ぐためにも遺言は重要です。
法律は、遺言について厳格な方式を定めています。
普通方式遺言として3つの方式があります。
①公正証書による遺言(民法969条)
②自筆証書による遺言(民法968条)
③秘密証書による遺言(民法970条)
この他に、特別方式遺言として以下のものがあります。
①死亡が危急に迫った者の臨終遺言
②伝染病で隔離された場所にいる者の遺言
③船舶中にいる者の遺言
④遭難船中にいる者の臨終遺言
しかし、最も多く利用されている方法は、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
なかでも、公正証書遺言を作っておくのが、最も確実な方法であるといえます。
公正証書遺言は、公証役場という場所に証人2人の立会いの下、遺言者が口述して作成します。
また、後にも検索で公正証書遺言があるかを調査することも出来ます。他の二つの方式は、家庭裁判所の検認など煩雑な手続きが必要であったり、偽造や隠匿の恐れがあります。
公正証書遺言のデメリットとしては、公証人への報酬等若干料金が掛かりますが、これで争いが防げるならばコスト的には安いものでしょう。 |
| ○ 遺産分割協議書の作成 |
遺産分割は、被相続人が遺産の分割を期間を定めて遺言で禁止した場合(5年を越えない期間)を除き、いつでもその相続人全員の協議によって分割することができます。(民法907条1項)
その協議が調わない場合、または協議出来ないときは、その分割を家庭裁判所に請求出来ます。(民法907条2項)
|
| ○ 相続人の調査 |
被相続人が死亡した場合、まず始めるものの一つに相続人の調査があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本を請求して相続人を決定します。
郵便で役所に請求することもできます。
注意が必要なのは、現代の活字体ならいざ知らず、明治、大正時代の戸籍は手書き、毛筆書きで古文書のようなミミズの這ったような文字の場合もあります。それを判読するのは至難の業です。
|
| ○ 相続財産の調査 |
相続人の調査と時を同じくして始めるものに、相続財産の調査があります。
中でも重要なのが負の遺産、債務の調査です。勝手に相続財産に手を付けると単純承認(民法920条)したものとして扱われますので注意が必要です。
相続財産に債務の方が多い場合は、自分に相続のあることを知った時から3カ月以内に相続の放棄(民法938条)を家庭裁判所に申述します。またこの期間は延長も可能です。
また財産が多いか債務が多いのか判断できない場合は、財産の範囲内で債務を負担する限定承認(民法922条)の方法もあります。これは相続人が複数あるときは全員で、家庭裁判所に財産目録を提出し、限定承認の申述をするものです。 |
| ○ 遺言執行手続 |
| 遺言の執行とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をその通りに実行することです。
遺言執行者は、 ①遺言で指定された者 又は ②家庭裁判所により選任された者 がなります。
遺言執行者は、遺産の預貯金債権の名義変更、払戻しのときなどに重要な役割を果たしてくれます。
したがって誠実で信頼できる人でなければなりません。場合によっては、遺言によって遺産をもらう人を遺言執行者とすることもできます。相続人が数人いる場合は、財産を最も多くもらう人を遺言執行者に指定しておくと、いろいろな事務処理をスムーズに取り運ぶことが出来るようです。
遺言執行者を必要とする場合、これを遺言で決めておきませんと、遺言者が死亡してから家庭裁判所で決めてもらうことになり、手数と時間がかかりますので、あらかじめ遺言の中で決めておくのがよいでしょう。なお当方を遺言執行者として遺言で指定することも出来ます。
|